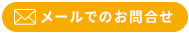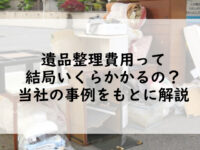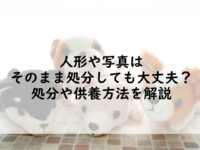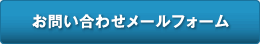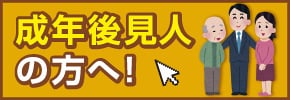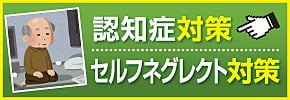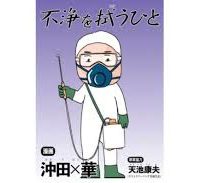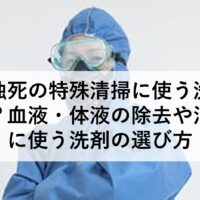納骨とは いつ行う?家族のみで行ってもいいのか
2024-06-17
生前整理・遺品整理のクヨカサービスでございます。当社は仙台市を中心に宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアにて遺品整理・特殊清掃のご依頼を承っております。
故人を見送った後、手元には遺骨が残ります。大切な人の遺骨は、どのように保管するのが良いのでしょうか。先祖代々続くお墓に納めたり、故人や遺族の意向で散骨や手元供養にしたり、その方法は様々です。
お墓などに遺骨を安置することを「納骨」と言います。
「納骨」を行う際には「納骨式」が行われることがあり、それは故人が安らかに眠れるよう、また遺族にとっては故人を供養し気持ちの整理をつけるための大切なものです。
「納骨」と「納骨式」について、以下で詳しく説明します。
納骨とは?
納骨とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂に納めることを指します。また、骨壺ごと納めたり、骨壺から遺骨を取り出したりと、宗教や地域によって方法は異なります。
遺骨の保管方法として、多くの人がイメージするものかと思います。しかし、必ずしもお墓などに納骨しなければならないというわけではありません。
遺骨を海や山などに撒く「散骨」や、自宅などに安置し供養する「手元供養」といった方法もあります。
故人の希望や遺族の意向を尊重し、双方にとって最も適した供養方法を選ぶことが重要です。そのためにも、様々な選択肢を考慮し、一番良い方法を決定しましょう。
納骨までの流れ
宗教や故人の事情によって手順が異なる場合がありますが、故人が亡くなってから納骨までの一般的な流れは以下の通りです。
- 死亡診断書の取得や死亡届の提出などの書類手続きを行う。
- 葬儀社へ連絡して葬儀の手配をし、日程や内容を決定する。
- 葬儀社により遺体が搬送・安置される。
- 通夜や葬式をとり行う。
- 火葬後、お骨上げが行われ、遺骨が骨壷へと納められる。
- 遺骨を受け取り、納骨まで自宅などで保管する。
- 納骨について詳細を決め、手続きを行う。
上記の流れの場合、故人が亡くなってから遺骨を手元で保管するまでは3日から一週間ほどかかります。一方、納骨まではどのくらいの期間があるのでしょうか。
いつまでに行う?四十九日まで?

納骨は、いつまでに行わなければならないという明確な期限はありません。
お墓の手配が済んでいる場合は、火葬が終わってすぐに納骨することもできますが、一般的には49日や一周忌などのタイミングで行われています。そうすることにより参列者も集まりやすく、また期限が無いことも、節目となる法要のタイミングが選ばれている理由の一つです。
家族のみでも納骨できる?
納骨は、家族のみで行っても問題ありません。
故人を送る最後の機会であるため、従来の納骨式では親戚や親しい友人などにも連絡を入れることもありました。しかし、誰を呼ばなければならないと決まりはないので、参列者は故人や遺族の意向で決めることができます。そのため昨今では家族のみの納骨も一般的になってきました。
また、参列者を呼ぶ、呼ばないに限らず、寺院墓地などに納骨する際は、僧侶を呼ぶのがベターです。僧侶を呼ばない場合、無断で納骨するのは失礼になってしまうため、納骨前にお寺へ一報入れましょう。
納骨式の流れ
家族のみの納骨の流れは一般的に次のようになりますが、地域や宗教などにより異なる場合があります。また、個人の事情や納骨式を行うかどうかでも流れは変わってきます。
家族のみで納骨する場合
- 納骨場所の選定
- 日程を決める ※寺院墓地などでは事前に連絡する
- 納骨場所へ遺骨を安置する
一方で、参列者や僧侶を呼んでの納骨式は以下のようになります。
僧侶を呼んで納骨する場合
- 納骨場所の選定
- 納骨式の準備:
- 日程や場所を決める
- 参列者を決め詳細を通知する
- 装飾品や花の手配など
- ※菩提寺などで僧侶を呼ぶ際はこのタイミングで予定を決める
- 納骨式の実施:
- 遺骨を骨壷に納める
- 家族や参列者により供養の儀式を行う
- 納骨場所へ遺骨を安置する
仏教の納骨式においては、僧侶を呼びお経を唱えたり、線香や花を供えたりします。キリスト教では讃美歌を歌ったり、献花が行われたりします。納骨式の内容は宗教によって異なるため、事前に確認するなど参列者も注意が必要です。
また、納骨する際は納骨式が行われるかどうかにかかわらず、故人を供養し、慰霊する機会が提供されます。
納骨に関するよくある疑問
納骨式の服装は何が適切?
一般的には礼服や喪服が適切ですが、地域や宗教、個人の好みなどによって異なる場合があります。親族も参列者も同じような服装で統一することが多いです。
お布施はいくら用意しておく??
お布施の金額は地域や宗教によって異なりますが、通常は30,000円から50,000円程度とされています。
納骨式の所要時間はどのくらい?
納骨式のみを行う場合は、一般的には30分から1時間を目安にすれば良いでしょう。
法要や会食を併せるとさらに時間がかかります。また、宗教によっては読経に時間を要するなど、参列者の人数によっても所要時間は大きく変わってきます。
納骨が終わったら遺品整理を始める
葬儀や納骨が終了したら、故人とのお別れの儀式が一段落しますね。
特に亡くなってから火葬までは、故人を静かに想う間も無く、あっという間に過ぎていきます。
一息ついたら、次は遺品整理に取り掛かってみるのはいかがでしょう。
故人の想い出が詰まった遺品の数々を整理することは、気持ちの準備が必要です。
無理はせず、ご自身や遺族の方々のタイミングで始めることが大切ですが、新たな一歩を踏み出すにはよいきっかけになるのではないでしょうか。
遺品の量が多すぎて個人では対処し切れない、遠方に住んでいて物理的に難しい、専門的な処理が必要などお悩みの際は、遺品整理のプロにお任せましょう。
大切な遺品の数々を、遺族に代わって丁寧に、速やかに整理してくれます。
宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアの遺品整理・特殊清掃は当社までご相談下さい。
メールでお見積もり依頼 >
電話で相談/0120-505-777(受付:9:00~20:00)
このページがあなたにとって役に立ったと感じたら下のボタンから共有をよろしくお願いします。