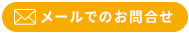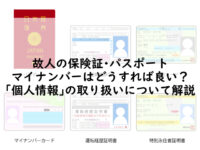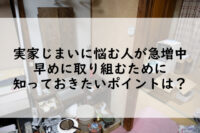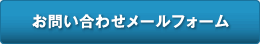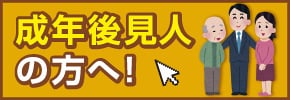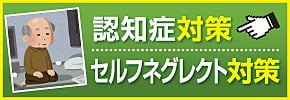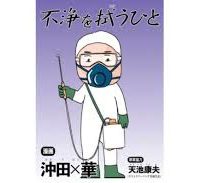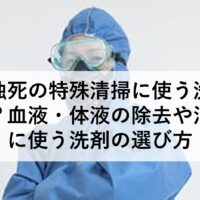水害後の片付けには何が必要?服装や道具を解説します
2024-10-23
遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスでございます。当社は仙台市を中心に宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアにて遺品整理のご依頼を承っております。
今年も全国各地で台風や線状降水帯による被害が多発しています。発生する地域も時期もばらばらで、どこに住んでいても水害の被害が起こり得るのだということを実感させられます。
万が一、浸水被害に遭った際、どのような点に注意しながら片付けを進めていけば良いのでしょうか?この記事では片付け前の注意点や服装、必要な道具について解説しています。
浸水した家を片付ける前にやっておくこと

浸水した家の片付けにはスピード感が求められますが、安全確保やその後の支援を受けるためにいくつかやっておくことがあります。ここでは、必ずやっておきたい事柄を3つに分けて解説しています。
ライフラインの確認
電気やガス、水道に被害が及んでいないか確認しましょう。浸水した電化製品はショートして発火する可能性があるので、プラグを抜いておきます。ブレーカーが落ちている場合は漏電の恐れがあるので、電力会社が安全を確認するまで電気を使わないようにしましょう。
同じようにプロパンガスのボンベが倒れている場合も、自分たちで直そうとせず業者による点検を待ちます。電気やガスを使えないのは不便ですが、漏電やガス漏れによる二次災害を防ぐためにも自己判断は禁物です。
被害状況を記録する
片付けを始める前に、浸水被害が起きた状況を細かく写真に撮っておきましょう。被害状況の記録は「罹災証明書」の発行や保険請求など、さまざまな場面で必要になります。どのくらいの高さまで浸水したのか、それによってどのような被害が起きたのかを記録していきます。
被害を受けた我が家を記録するのはつらい作業ですが、生活再建のために公的支援や保険は強い味方になります。細かく具体的に記録を残しておくことが大切です。
防犯対策を行う
悲しいことですが大きな災害が起きたあとの住宅地では、窃盗や強盗などが起きることがあります。貴重品を安全な場所に移すとともに、扉や窓の鍵が閉まるかよく確認しておくことをおすすめします。
もし鍵が壊れている場合は、そこから侵入できないようにワイヤーで留めるなどの対策を取りましょう。
水害後の片付けは感染症とケガの予防がポイント

水害が起きたあとは感染症やケガなどの二次被害にも気を付ける必要があります。ここでは、片付けを始める前に知っておきたい注意点や、怪我などを防ぐ服装について解説しています。
水害後に起きうる健康被害
日本予防医学協会では、洪水をはじめとする水害によって引き起こされる健康被害として以下のようなものを挙げています。
・コレラ、赤痢、腸チフスなどの水が媒介する感染症
・インフルエンザ、結核、髄膜炎などの呼吸器感染症
・食中毒
・低体温症
・破傷風
・熱中症
水害の際、家屋に流れ込んでくる汚水には有害やウイルスが含まれています。また、泥にまみれた状態ではガラスや瓦礫などが見分けづらく、負傷のリスクも非常に高くなるのです。
特に被災直後はきれいな水や医薬品が不足しやすく、万が一傷を負っても消毒ができないケースも珍しくありません。よく知っている場所にも思いがけない危険が潜んでいることを踏まえて、慎重に行動するようにしましょう。
参考:一般財団法人 日本予防医学協会「企業における洪水被害に対する健康管理ハンドブック」
片付けの時の服装や装備
水害後の片付けを行う際の服装は、手足をしっかり防護することとマスクをつけることが大切です。以下のような服装を参考に、事故やケガから身を守りましょう。
・ヘルメット
・ゴーグル
・マスク(防塵マスクがベスト)
・長袖長ズボン
・手袋(軍手+ゴム手袋)
・安全靴
暑い時期に身体をしっかり覆うのはつらいですが、雑菌やウイルスの多い環境下では、いつもなら気にもならない傷でも大きなダメージへつながる可能性があります。最大限の注意を払い、ケガや事故を防ぎましょう。
必要な道具
水害後の片付けには、以下のような道具が必要です。被災直後はすぐに片付けなくてはと気が急いてしまいますが、必要な装備や道具が揃っていないままに動くと、効率が悪いだけでなく二次被害を受ける可能性もあります。
まずは落ち着いて以下のような道具を揃えていきましょう。
・ほうきやちりとり
・モップ
・雑巾とバケツ
・スコップ
・ペンチなどの工具
・ゴミ袋
・ダンボールやコンテナ
・ヘッドライト
・ガムテープ
・洗剤
・消毒液
子どもや高齢者を清掃に参加させても大丈夫か

これまでにも解説してきましたが、水害が起きた現場には有害なウイルスや雑菌、ガラス、瓦礫といった危険がたくさんあります。手足の先や口元をしっかり防護して、二次被害を受けないように心がけましょう。
また、少しでも人手がほしいからと子どもも作業に参加することがありますが、小児科医は可能な限り10代の子どもは清掃に関わるべきではないと警告しています。有害物質にさらされやすいというリスクにくわえて、好奇心から危険なものに触れてしまう可能性があるからです。
やむを得ず現場に連れていく場合は、子どもの安全に充分留意することも大切です。
同じように呼吸器に基礎疾患を抱えている方や抵抗力の低い高齢者にとっても、水害現場は非常に危険な場所です。片付けに参加するかの判断は、慎重に行うことをおすすめします。
参考:ヨミドクター
無理をせずにボランティアや業者を頼ることも大切

水害の後片付けは精神的、体力的に非常に負担が大きい作業です。特に床上浸水している場合、自分たちだけで復旧するのは困難でしょう。ある程度の安全が確保できたら、行政やボランティアの支援を依頼するとともに、専門業者への依頼も検討しましょう。
特に水害後の脱臭・消毒作業には、プロ仕様の機材や清掃技術が必要です。クヨカサービスでは水害臭対策や原状回復リフォームのご相談を承っております。
万が一の際は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
このページがあなたにとって役に立ったと感じたら下のボタンから共有をよろしくお願いします。