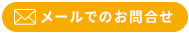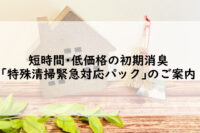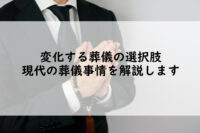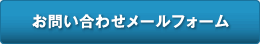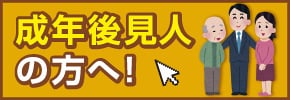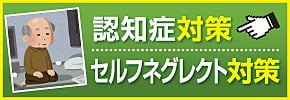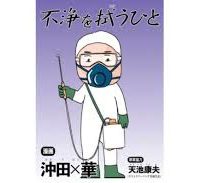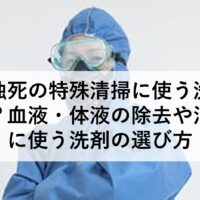事故物件とはどういうもの?ガイドラインをもとに解説
2025-01-22
遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスでございます。当社は仙台市を中心に宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアにて遺品整理や特殊清掃のご依頼を承っております。
「事故物件」という言葉から、どのようなイメージを抱くでしょうか。孤独死や自殺が関係する物件と聞くと、不安を覚える方も多いかもしれません。
少子高齢化の進行や単身世帯の増加により、誰にも看取られることなくお部屋で亡くなる方は増加傾向にあると考えられています。この現象は社会問題としても注目され、さまざまな議論や対策が行われるようになりました。
この記事では令和3年に発表された新しいガイドラインをもとに、事故物件とはどのようなものかを分かりやすく解説します。
「事故物件」という言葉が広まったのは90年代

孤独死という言葉が一般的に使われるようになった歴史は意外と古く、1995年に起きた阪神・淡路大震災以降だといわれています。孤独死が社会問題として注目されるのと同時に、不動産業界で使われていた「事故物件」という言葉も広く知られるようになりました。
しかしこれまでは事故物件に明確な定義がなく、業者の独自基準で運用されてきたため、物件をどのように取り扱うべきか混乱が生じることもありました。
事故物件は不動産オーナーや管理会社にとって、非常に厄介な問題です。家賃を下げても入居者が見つかりにくいだけでなく、周辺地域への風評被害が広がることもあります。
特に住民の入れ替わりが少ない地方都市では噂だけが残ってしまい、心霊スポットのように扱われることも。風評が風評を呼び、最終的には建物全体を取り壊さざるを得なかったケースも珍しくありません。
病死や事故死、自殺、他殺など、室内での死亡原因はさまざまですが、どのケースを事故物件とするかは業者ごとに判断が異なっていました。そのため同じ物件でも業者によって事故物件とみなされる場合と、そうでない場合があったのです。
明確な判断基準がないことも、さらなる誤解を招く原因のひとつになっていたといえるでしょう。
「心理的瑕疵」とはどのようなもの?

「瑕疵」とは傷や欠点などを指す言葉です。入居者が「この部屋に住むのは避けたい」と感じるような要因を不動産業界では「心理的瑕疵」と呼び、通常の物件と区別してきました。
心理的瑕疵があるとみなされる物件には、孤独死や事件事故の現場になったところだけでなく、反社会的勢力の拠点や一般的に嫌悪されることの多い施設も含まれます。
これらの情報を意図的に隠して入居者が不利益を受けることがないよう、仲介業者は心理的瑕疵を告知するよう宅地建物取引業法によって義務付けられています。
しかし告知の範囲や期間については統一した見解がなく、基準があいまいでした。ガイドラインの制定は、物件を貸す(売る)側と借りる(買う)側どちらにとっても有益だといえるでしょう。
令和3年に告知に関するガイドラインが発表

令和3年10月、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。このガイドラインは裁判例や過去の事例をもとに、事故物件の取り扱いに関する基準を示すものです。
ガイドラインに法的拘束力はありませんが「現時点で妥当とされる一般的な基準」という現実的な判断基準を提供しています。
このガイドラインが制定された背景には、高齢者の単身世帯が増加しているという事情も関係しています。お部屋で亡くなるリスクが高いとされる、単身高齢者の入居を敬遠する不動産オーナーは少なくありません。新たな判断基準を示すことで、単身高齢者の入居を促すという目的もあるのです
参考:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
自然死や日常生活の事故は告知不要
ガイドラインでは、以下のようなケースは告知対象外とされています。
・自然死
・日常生活に起因する不慮の事故
ガイドラインでは自宅で生じた人の死の約9割が老衰や病死など、いわゆる自然死であることを指摘しています。
自宅の階段からの転落や入浴中の事故、食事中の誤嚥といった日常生活の中で起きた死について、人間が生活している以上は予想できることであり、買主・借主の判断に重大な影響を及ぼす可能性は低いと認めたのです。
共用部分の事故も告知対象
ガイドラインでは、共用部分や同じ建物の別の部屋で起きた事故についても言及しています。
エレベーターやエントランスなど、生活するうえで必ず使用する共用部分での事故や事件については、居室と同じく告知が必要です。
一方で普段使用しない共用部分や、同じ建物内の別の部屋については告知不要とされました。この取り扱いの違いは、実際の生活にどのくらい影響するかによって基準が定められています。
特殊清掃が必要な場合は例外
自然死や不慮の事故であっても特殊清掃が必要な場合は、例外として告知対象になります。特殊清掃が発生するケースは臭気や害虫の被害を受ける可能性があること、また、心理的な影響も大きいためです。
このような場合、告知を行うことで入居者や購入者が十分な判断材料を得られるよう、告知をしなければなりません。
つまりガイドラインにおける事故物件とは、以下の条件に該当するものを指します。
・自然死や日常生活の事故ではない死
・死因にかかわらず、特殊清掃が必要になった死
告知期間は原則3年とされていますが、事案の影響度に応じて柔軟に対応することが求められています。
事故物件へのマイナスイメージを払う取り組みも

事故物件に対する過度なマイナスイメージは、高齢者の入居を妨げるなど、社会的な影響も少なくありません。ガイドラインの導入はこういった課題への解決に貢献する効果も期待されています。
事故物件を正しく流通させる取り組みの一環として、事故発生時の特殊清掃から事故物件の買取、リノベーション、再販売までを一貫して行う会社も登場し話題を集めました。
クヨカサービスでも特殊清掃からリフォームまで、ワンストップで対応できるシステムを整えております。お困りの方は、是非お気軽にご相談ください。
このページがあなたにとって役に立ったと感じたら下のボタンから共有をよろしくお願いします。